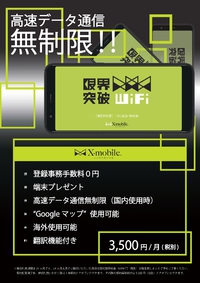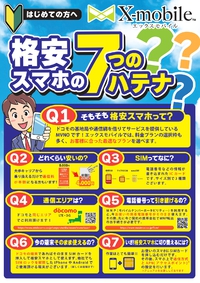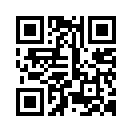2009年04月03日
シーサーの日
今日4月3日は、『シーサーの日』です

「シー(4)サー(3)」の語呂合せからだとか・・・

沖縄の家で、ほとんど見られるシーサー
 は、
は、
昔、中国からわたってきました

魔よけの獅子(ライオン)像であり、もともとはグスク(城)や寺社の門前、
王陵、集落の入り口などに設置され、
そこに住む人、村に災いをもたらす悪霊を追い払う魔除け、
災難避けの意味を持つ「村落獅子」と呼ばれる石造の獅子であったものが、
19世紀後半ごろから、民家にも赤瓦の使用が許されると、
民家の屋根にも据え付けられるようになったそうです
どうして、屋根の上に据えられるようになったのかはよく判らないみたいですが、
首里城の正殿隅棟(すみむね)中央あたりの前面と背面に
1対ずつ「獅子面」の鬼瓦があり、これが「屋根獅子」の始まりと言われているそうです
シーサーは元々は単体で設置されていたものですが、
仏教思想の影響からか、阿吽像一対で置かれることが多くなったそうです


そこで、宜野湾電設にもシーサーを置いて見ました


名前は『ギノデンシーサー』


『ダイビングシーサー』 と 『三味線シーサー』です
これから宜野湾電設を守ってくれることでしょう



「シー(4)サー(3)」の語呂合せからだとか・・・


沖縄の家で、ほとんど見られるシーサー

 は、
は、昔、中国からわたってきました


魔よけの獅子(ライオン)像であり、もともとはグスク(城)や寺社の門前、
王陵、集落の入り口などに設置され、
そこに住む人、村に災いをもたらす悪霊を追い払う魔除け、
災難避けの意味を持つ「村落獅子」と呼ばれる石造の獅子であったものが、
19世紀後半ごろから、民家にも赤瓦の使用が許されると、
民家の屋根にも据え付けられるようになったそうです

どうして、屋根の上に据えられるようになったのかはよく判らないみたいですが、
首里城の正殿隅棟(すみむね)中央あたりの前面と背面に
1対ずつ「獅子面」の鬼瓦があり、これが「屋根獅子」の始まりと言われているそうです

シーサーは元々は単体で設置されていたものですが、
仏教思想の影響からか、阿吽像一対で置かれることが多くなったそうです



そこで、宜野湾電設にもシーサーを置いて見ました



名前は『ギノデンシーサー』


『ダイビングシーサー』 と 『三味線シーサー』です

これから宜野湾電設を守ってくれることでしょう